大人になるとゲームを楽しめなくなる5つの理由【年を取った証拠?】

高校まではかなりのゲーマー、カスカスです。
さて、こんな方はいませんか?
・昔ほどゲームが面白いと感じなくなった
・大人になってから純粋に楽しめなくなった
全員ではないと思いますが、大人になるとゲームを楽しめなくなる人が多くなるようです。

実際にネットでも、
ゲーム 純粋に楽しめない
ゲーム 楽しくなくなった
社会人 ゲーム楽しめない
といったことが検索されているようです。
子供の頃は「早くお金を稼いで色んなゲームを買いたい」なんて思っていましたが、いざ大人になって見るとそこまでゲームに没頭することもなくなりました。

カスカス
なぜ大人になるとゲームが楽しめなくなるのか?
その理由を考えてみます。
なぜ大人になるとゲームを楽しめなくなるのか?
子供の頃は、ただただゲームに没頭していました。

カスカス
あれだけゲームが楽しくて仕方なったのに、大人になると急に楽しめなくなる。
なぜ大人になるとゲームを楽しめなくなるのか?
その理由は以下の5つ。
・ゲーム以外の娯楽が充実しているから
・話し相手がいないから
・新鮮味がなくなったから
・なんやかんやでリアルが楽しいから
プレイ時間の減少

まず一つ目は『プレイ時間の減少』です。
子供の頃は無駄に時間があったので、放課後はもちろんのこと、休日なんかは朝から晩までゲームに没頭していました。
しかし大人になると、仕事や生活などでゲームに割く時間が減ってしまいます。
中には、仕事の疲れでゲームする気力が湧かないって人もいるでしょう。
そうこうしているうちに「全然ゲームできない、もういいや」となってしまう。
子供の時のような「夜更かししてゲームをやる」ってことも肉体的に厳しくなっているので、大人になると自然とプレイ時間は減っていくのだと思います。

カスカス
ゲーム以外の娯楽が充実しているから

子供の頃の楽しみと言えば、ゲームくらいしかありませんでした。
そりゃそうです。
限られたお小遣いと行動の中で楽しめる娯楽がゲームだったんですから。
しかし大人になってお金と行動の幅が広がると、ゲーム以外の選択肢が多くなります。
・旅行
・アウトドア
・ギャンブル
などなど
『ゲーム以外の娯楽が充実している』ことも、ゲームを楽しめなくなった理由でしょう。

カスカス
話し相手がいないから

子供の頃は、話ながら一緒にプレイするってことがあったし、攻略法を教え合いながらプレイってのも多くありました。
・どうやってアイテムを手に入れたか
一人プレイであるRPGやシミュレーションだって、誰かと共有できるから面白いのであって、1人黙々と進めても楽しくありません。

カスカス
しかし周りの友人たちがゲームを引退したり、現役であってもプレイするゲームが違ったりと、大人になると『話し相手がいない』ことが多くなってきます。
攻略法も聞かずともネットで調べると簡単に出てきます。
オンラインゲームで話すこともできますが、知り合いならともかく、知らない人とゲラゲラ笑いながらプレイって難しいですからね。

カスカス
新鮮味がなくなったから

大人うんぬんではなく、ゲームの『新鮮味がなくなったから』という理由もあります。
私はスーファミスタート世代なのですが、毎年のように新しいゲーム機、毎月のようにゲームソフトが登場しました。
グラフィックが良くなったり、新しいシステムができたり・・・と、毎回のように感動していた記憶があります。
そのたびに何を買うか迷ったし、選ぶ楽しみもありました。

カスカス
しかし今はどうでしょう?
グラフィックはほぼ限界に来ていますし、ゲーム会社が減っているせいもあってソフトの選択肢も少ない。
今は新作ゲームに対する感動がほとんどありません。

カスカス
なんやかんやでリアルが楽しいから

最終的にはこれに行き着きます。
『なんやかんやでリアルが楽しい』
当時の子供にとってゲームは、その時出来ないことの【疑似体験】だったと思います。
だからこそ、スポーツ系ゲームやすごろく系ゲームも売れたわけです。
しかし大人になると、ゲームでしかできなかったことがリアルで体験できるようになります。
恋愛然り、マネーゲーム然り、スポーツ然り。
社会人として生きていること自体がある意味ゲームなので、疑似体験であるゲームが面白くなくなってしまったのかもしれません。

カスカス
大人でもゲームを楽しむ方法
とはいえ、暇つぶしがてらゲームを楽しみたい時ってありますよね。
そこで大人でもゲームを楽しむ方法として、『ゲーム実況』や『オンラインゲーム』がオススメです。
『ゲーム実況』なら誰かに観て貰える楽しみがありますし、『オンラインゲーム』なら同じゲームを楽しむ人と繋がることが可能です。
そこから有名になって“お金”が稼げるようになれば、また違った楽しみを味わうことだってできます。
大人でもゲームを楽しみたいときは、ただゲームするのではなく、+αで何かを始めてみるのもいいかもしれません。
ゲームが楽しめなくなるのは、年をとった証拠

私自身、未だにゲームを嗜んでいます。
しかし昔ほど没頭することはなくなりました。
でもこれって、自然なことなのかなって思います。
老後は園芸や家庭菜園・ゲートボールにハマるように、年齢を重ねるごとに趣味・娯楽が変わっていくのかもしれません。
ゲームを楽しめなくなってしまうこともその一つ。
たぶん違う楽しみを知ってしまったからだと思います。
なのでゲームを楽しめなくなったのはネガティブなことではなく、年を取り楽しみ方に対する視野が広がったという事だと思うので、ポジティブに考えた方がいいでしょう。

カスカス




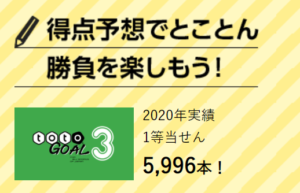


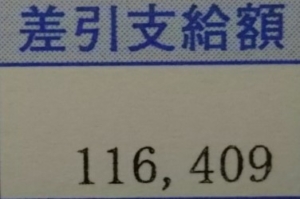



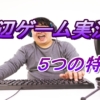


















ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません